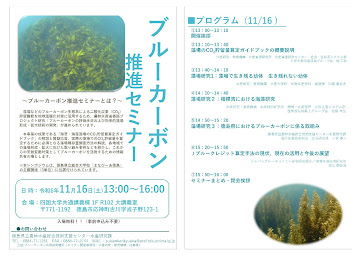令和7年3月
令和7年3月になりました。早いもので令和6年4月17日に入学した5人は、入学直後のオリエンテーションから始まり、9月までの現場研修、座学、各種資格取得、10月以降の親方の下での約半年間にわたるインターンシップを終え、無事卒業の運びとなりました。研修生は常に安全を常に心がけ、大きなトラブルもなく、研修の全課程を無事終えられたくましく成長されたことを、事務局として非常に頼もしく感じております。なお、国支援金(準備型)を活用した研修生4名は、今月から親方や会社と雇用契約等を締結し、長期研修に入りました。
また、2月末まで募集していた令和8年度研修生については、第2回目(最終)の選考審査会を上旬に実施し、合計15名が合格となりました。
〇各研修生の就業先(3/1 or 4/1~)
国次世代人材投資(準備型)事業を活用していた4名(専攻コース3名、一般コース1名)は、それぞれ北灘漁協、和田島漁協及び椿泊漁協の個人又は漁業会社において、国長期研修支援制度を活用し、就業しながら独立(うち3名)を目指すこととなりました。また、専攻コースのうち漁家子弟1名は引き続き親元で研修し、4月から独立予定となっております。
〇令和6年度第8期とくしま漁業アカデミー卒業式
実施日 令和7年3月18日(火) 11:00~11:45
場 所 徳島市東沖州2-13 徳島県水産会館4階大研修室
卒業生 5名
令和6年4月17日(水)に入学した第7期生5名全員が晴れて3月18日(火)に卒業しました。当日は中藤理事長から卒業証書を受け取り、理事長式辞の後、来賓の徳島県漁連久米会長から卒業生に対し、心のこもった励ましのお言葉をいただきました。卒業生を代表して、最年少の大西さんからお礼の言葉を述べ、最後に記念撮影を行い卒業式は無事終了しました。この1年間で多くの漁協の方々の丁寧な指導と親方の実践的な指導の下、たくましく成長した研修生の姿がありました。
理事長式辞

















%E9%95%B7%E6%9C%9F%E7%A0%94%E4%BF%AE%E7%A7%BB%E8%A1%8C%E6%89%93%E5%90%88%E3%81%9B%20003.jpg)